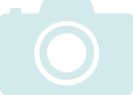
高知大学のクマムシ。これこそが私を高知大学に導いてくれたきっかけである。当時高校2年だった私は生物を勉強したいという気持ちはあったものの大学を決め切れていなかった。ふと、愛用の資料集を見ていたところ、目次直前の最後のコラム、たった5行程度の文章と写真でクマムシの説明がされていた。低温、高温、高圧、放射線に耐えられる…。ん?これってすごすぎないか?どうしてこんなに耐性がある?本当に人間と同じこの世の生物か?と興味をそそられた。調べてみればクマムシは解明されてないことだらけ。「これだー!」っと研究対象が決定した。
ただ、どこの大学に研究している先生がいるんだ?T大学?KG大学?は?都会の大学には行きたくない。どこか地方で…と思っていたところ、高知大学のクマムシというサイトを発見した。そこにはクマムシの写真と種名、クマムシの採取方法などが記載されていた。高知かー。地方で行ったことがない。よし、高知大だ。私の進学先が決まった。
8月、コロナ禍前のオープンキャンパスで高知に来た。空港を降りた最初の感覚は、蒸し暑い。やっぱり南国土佐というだけある。翌週によさこい祭りを控える中、中心街では練習の声となる子が響いていた。そんな中、路面電車で朝倉キャンパスへ。ついに理工学部の生物紹介の見学、と思えば教室の端に顕微鏡が5台。覗いてみれば、目の前にあのクマムシが!遂に高知大でクマムシを研究しているM先生と出会った。聞けば、M先生の専門はコケ植物であり、クマムシは専門ではないという。ただ、スマホで撮影したクマムシの映像も見て、ますます進学する意欲が高まった。
そこで、学校推薦を受けることに決めた。万全の対策を講じたうえで推薦当日。会場の332番教室に踏み入れた瞬間、衝撃を受けた。面接官3人の中にきっかけとなったM先生がいる!会場は2箇所あったのに、まさか高知大に決めたきっかけとなった先生がいたとは。面接では、自分のクマムシに対する熱意を強く伝えることができた。緊張よりも衝撃が強かった面接であった。